20250713日曜午後礼拝
聖書:ルカ8:5−8
題目:種を蒔き続けよう
賛美:488、489
説教:高曜翰 牧師
“「種まきが種をまきに出て行った。まいているうちに、ある種は道ばたに落ち、踏みつけられ、そして空の鳥に食べられてしまった。 ほかの種は岩の上に落ち、はえはしたが水気がないので枯れてしまった。 ほかの種は、いばらの間に落ちたので、いばらも一緒に茂ってきて、それをふさいでしまった。 ところが、ほかの種は良い地に落ちたので、はえ育って百倍もの実を結んだ」。こう語られたのち、声をあげて「聞く耳のある者は聞くがよい」と言われた。”
ルカによる福音書 8:5-8 口語訳
1。宮沢賢治
宮沢賢治(1896-1933)は岩手県の仏教(日蓮宗)の家系に生まれた宗教家でした。自分の救いよりも他人の救いに重きを置き、あの世よりもこの世で仏国土を実現する教えに感銘を受けたようです。そして宮沢は、すべての人が、自分ではなく隣人を1番に考えることができれば、幸せな社会を実現できると考えました。そして自分の理想の幸せとは、全ての人の幸せを願い、そのために尽くすことだと考えました。
結核で死期が近くなった時、宮沢は内村鑑三のキリスト者としての生き方に感銘を受け、自分の理想の生活を実行した人だと評価をしています。その影響で聖書を読むようになり、真の幸せとは、地上での人間の絶え間ない努力ではなく、天から来ることを理解しました。宮沢は仏教の伝道活動のため、銀河鉄道の夜を書き始めましたが、最後のクライマックスでは最大限の自己犠牲の象徴である十字架を出さないわけにはいかなくなりました。
私たちの救いと幸せは、私たちの努力で作られるのではありません。宮沢が気づいたように、天からくる神の恵みによって達成されるものです。今日の種蒔きの例えは、御言葉を聞いて多くの実を結ぶ人を見分けるための知恵や、多くの人々が御言葉を受け入れるようになるための技術や、まして自分が多くの実を結ぶため方法を教えるためのお話ではありません。種蒔きのお話は、宮沢が気づいたような真理に基づいて、御言葉を宣べ伝える人生を送るための心構えについてのメッセージです。
2。種蒔きのたとえ
まずは内容を見てみましょう。種蒔きが蒔いた種の一つ目は、畑の固い道端部分に落ちましたが、鳥が見つけて食べてしまいました。二つ目は、土の薄い岩地に落ちましたが、焼けつく熱で枯れてしまいました。三つ目は、イバラの中に落ちましたが、イバラに負けて成長できませんでした。四つ目は良い地に落ちたので、100倍の実を結びました。11−15節に書かれたイエスの解釈を見ると、種は御言葉、土は御言葉を聞く人の心、種蒔きは御言葉を伝える人であることがわかります。また、実りは救いを指し、1〜3つ目の地は救いに至らなかったことがわかります。道端の心は頑固な心であり、心に御言葉が入っていきません。岩地の心は迫害に弱い心であり、信仰を捨ててしまいます。イバラの地の心は誘惑に弱い心であり、信仰が育ちません。良い地の心は、御言葉通りに生きることを喜びとし、救いに至る心です。
それではこの例え話の結論は何でしょうか?困難や誘惑に打ち勝ち、御言葉を受け入れる柔らかい心を持って救われましょう、ということでしょうか?それなら、なぜ耕すことや雑草を引き抜く表現が出てこないのでしょうか。また、群集には真意を隠し、弟子には詳しく説明した意味がわかりません。「聞く耳のある者は聞くがよい」とはどういうことでしょうか?
弟子たちだけに打ち明けたのは、宣教を行う弟子たちだけが理解できればいいからです。すると、イエスが弟子たちに望むのは、無闇にでなく、御言葉を受け入れられる心の人を探しながら宣教をしなさいということでしょうか?しかし、これはすべての人に福音を述べ伝えなさいという神様の計画(大宣教命令)と反しています。それではイエスは弟子たちに何を伝えようとしたのでしょうか?
種蒔きの例えの核心は、落胆せず、偏見なく全ての人に御言葉を伝えましょう、ということです。イエスは伝道者を励ますためにこの例え話をしました。何故そう言えるのでしょうか?それはイエスがこの比喩がムステリオン(奥義)だと言っているからです。ムステリオンとは、ユダヤ人だけでなく、異邦人もイエスを通して救われるということです(エペソ3:6)。当時ユダヤ人たちは理解できませんでした。しかし、神様は全ての人を愛しているので、全ての人が救われることを望んでいるのです。当初、神様はユダヤ人を通して全ての人が救われることを計画しました(創世記12:3)。しかしユダヤ人がその役目を果たさなかったため、異邦人に先に救いが行くようになったのです。しかし神様は、ユダヤ人を捨てませんでした。それほど両方を愛しており、救いたいのです。
3。奥義の観点から見る種蒔きの比喩の意味
この例え話から3つの事実を確認しましょう。実を結ぶのは種蒔きの問題ではなく、受け入れる土の状態による、ということです。種蒔きの技量が優れているから実を結ぶのではありません。イエスも、ナザレやコラジン、ベツサイダ、カペナウム、サマリヤでの伝道に苦労されました。もし伝道者の技量によって結果が変わるなら、救いが人の努力によるということになります。しかしそうではありません。人の救いは100%神様の技によるものです。伝道者の技量によるというのなら、救われなかった場合の罪悪感は凄まじいものとなり、優れた人しか伝道してはいけないことになります。しかしそうではありません。イエスは全ての救われた者に対して福音を伝える使命を与えました。実る実らない問題は、伝道者ではなく、御言葉を聞く人の心の状態によるのです。
そして、実を結ぶのは少しの土地だが、その収穫は大きい、ということです。残念ながら、全ての地が種を受け入れ、実を結ぶわけではありません。「残る者」(イザヤ10:11、エレミヤ23:3)や「狭き門」(マタイ7:13)という言葉から、聖書は一貫して一部のものが救われることを教えています。全ての人に御言葉を伝えるように教えますが、実際の救いは別なのです。どうせ理解できないと思われる群衆に比喩で説明するのは、イエスが意地悪だからではありません。群衆に埋もれているが、実を結ぶ土地の心を持っている者に奥義を届けるためです。それだけ受け入れる者が少ないということですが、その反面その少数を大切に考えているから話すのです。そしてその少数から出る実りは想像以上になります。後には12弟子がペンテコステで3000人の仲間を作流ようになります(使徒2:41)。実る実らない問題は、元々実る土地が少しなので、だからその分その少数が大切なのです。
だから、落胆せずに、全ての土地に種を蒔いていこう、ということです。良い土地の人々である私たちの役割は神の栄光のために種を蒔くことです。多くの実りを作ることが役割ではありません。実りを作る結果もその栄光も、神様のものであり、私たちのものではないからです。伝道活動を続けると、自分本位の考えで不満が出てきます。「私がこれだけ努力したのに、実りがないなんて、神様ひどい!」「救われない人々がいるなんて、無駄に働かせて疲れさせて、神様ひどい!」「わかりにくくして、詳しく説明してくれないイエス様ひどい!」などです。しかし、全ての人に伝えたら全ての人が救われる、という考え自体が間違いなのです。
実りが目的ですが、種を蒔くことが私たちの役割です。そして成長させることは神様の役割です。そしてその実りは神様お陰です。私たちに成長させる力はありませんが、種を蒔かなければ実こともありません。例えば、伝道したが、誰も教会に連れて来れなかった聖徒と、1000人を教会に連れてきた聖徒とでは、どちらが神様に喜ばれる聖徒でしょうか?答えは両方同じです。逆に、1000人連れてきたとしても、自慢するのなら、神の栄光にならないので、神様は喜びません。種を蒔いても、自分が称賛を受けるためなら、その伝道、その奉仕は間違っています。
宮沢が斎藤宗次郎や内村鑑三に感銘を受けたのは、大きな成果や大胆な心ではなく、すべての人に神の愛を伝えるキリスト者としてのその姿そのものです。私たちも大きな成果を求めるのではなく、キリスト者として神の愛を伝える人生を送りましょう。全ての人に福音を宣べ伝えられるように種を蒔き続けることが、私たちに与えられた使命なのです。
4。まとめ
❶ 実を結ぶのは種蒔きではなく、受け入れる土の状態による。
❷ 実を結ぶのは少しの土地だが、その収穫は大きい。
❸ だから落胆せずに、全ての土地に種を蒔いていこう。


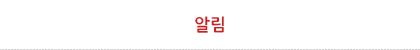
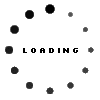
댓글0개